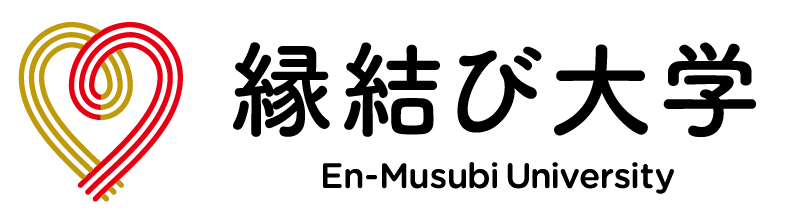奈良市杉岡華邨書道美術館で日本の美を堪能!ならまちエリアで楽しむカップルデート
この記事では、書道作品を展示する「奈良市杉岡華邨書道美術館」を中心に歴史ある町並みの「ならまち」エリアを楽しめるデートプランを紹介します。
ならまちエリアにある奈良市杉岡華邨書道美術館は、「かな書」と呼ばれる流麗な美しさを持つ書体の作品をメインに展示する書道専門の美術館です。
美術館は近鉄奈良駅や奈良公園などの観光スポットから徒歩圏内にあり、アクセスも便利です。歴史ある寺社や商店街、飲食店などが立ち並ぶならまちエリアで日本文化を堪能することができます。
「奈良市杉岡華邨書道美術館をメインに"ならまち"を楽しみ尽くしたい!」というカップルにぴったりのデートプランをこれからご紹介します。
おすすめカップル:書道に興味がある・アート好き
どんなデート?:日本文化を味わう・体験する
目安時間:6~7時間
目安予算:2人で19,000円
「縁結び大学」や「マリピタ」で、取材記事の企画・編集を担当、編集歴3年。地方自治体や観光協会への取材記事を数多く手掛け、これまでに約3,000件を担当。地方自治体が取り組む最新の婚活情報や観光協会イチオシのデートスポットなどを読者へお届け。
概要:杉岡華邨書道美術館とならまちエリアで楽しむ和のデートプラン
今回ご紹介するのは、書道文化を伝える「奈良市杉岡華邨書道美術館」を中心に歴史ある「ならまち」エリアを堪能する、見て・食べて楽しめるデートプランです。
| 12:30~14:00 | カナカナでランチ |
|---|---|
| 14:15~15:15 | 奈良市杉岡華邨書道美術館を堪能 |
| 15:30~16:30 | 奈良公園を散策 |
| 16:45~17:45 | もちいどのセンター街でお買い物 |
| 18:00~ | 居酒屋つのふりでディナー |
※空いている時間は移動時間です
美術館に向かう前に、古民家カフェ「カナカナ」でランチをとりましょう。近鉄奈良駅から出発し、風情ある町並みのならまちを抜けてカフェへ向かいます。
カナカナには座敷席とテーブル席があり、座敷では足を伸ばしてくつろげます。「鮭の南蛮漬け」や「高菜のせごはん」など心温まる優しい和食を味わえるので、ならまち散策のデートにぴったりです。
奈良公園を散策したあとは、歴史ある町並みのならまちエリアを巡りつつ「もちいどのセンター街」でお買い物を楽しみましょう。和雑貨店やハンドメイドショップ、和菓子屋など約100店舗が軒を連ね、二人の思い出の品を見つけられるでしょう。
最後は、和モダンな雰囲気の「居酒屋つのふり」でディナーを楽しみます。個室完備のおしゃれな店内には、ガラス張りの床下に小川が流れる独特の演出も。非日常的な空間で奈良の地酒や自家菜園の野菜を使った料理を味わい、心ゆくまで日本文化を堪能しましょう。
ここからは今回のデートプランのメインである「奈良市杉岡華邨書道美術館」について、詳しく紹介していきます。
杉岡華邨書道美術館で出会う美しいかな書の世界

「書道」と聞くと、どのようなイメージを思い浮かべますか?お正月の書き初めや小学校での書道の授業を思い出す方も多いかもしれません。
日本文化に深く根付いており、誰もが一度は触れたことのある書道ですが、その歴史は1500年以上前にさかのぼります。書き方にも楷書、行書、草書など様々な種類があります。その中でも、流れるような美しさが特徴の「かな書」と呼ばれる書体の作品をメインに展示しているのが、今回ご紹介する「奈良市杉岡華邨書道美術館」です。
この美術館で展示されている「かな書」という書体の書道作品は、文字の自由な配置や墨の濃淡によってまるで絵画を鑑賞するような感覚で楽しむことができます。書道は難しそうだと感じる人でも、一度見てみると新しい魅力に気づくかもしれません。
美術館の名前の由来は奈良に縁の深い書家「杉岡華邨(すぎおかかそん)」からきています。生前の杉岡氏が奈良市に作品を寄贈したことをきっかけに、書道文化を後世に伝えていきたいという願いを込めて2001年に開館されました。
平城京跡に近い、歴史豊かな「ならまちエリア」の中にたたずむ趣のある美術館で、日本の伝統的な書道文化を味わうことができます。
今回は、美術館の魅力や見どころについて、事務長兼学芸員を務める松村さんにお話を伺いました。
かな書から学ぶ日本の美意識と精神性
編集部
最初に、奈良市杉岡華邨書道美術館にてメインで展示している作品についてお聞かせください。
松村さん
当館は、書道を専門として展示する美術館です。
文化勲章受章者で現代かな書の第一人者であった杉岡華邨氏(1913~2012)の作品を中心に、現代書道作品を紹介しております。杉岡華邨氏の古典の趣きが感じられる初期の細字作品から、晩年の精神性豊かな大字作品までご鑑賞いただけます。

▲展示室には横長の額縁に飾られたかな書作品や冊子等が展示されている
編集部
美術館を訪れた人にはどんなことを学んだり、感じたりしてほしいでしょうか。
松村さん
展示されている書道作品から日本人の精神性や美意識の原点を感じていただければ幸いです。
日本独自の芸術であるかな書は、平安中期の貴族文化の中で芸術として完成の域に達しました。そこには漢字の書とは異なる日本人独自の感性から生み出された、流麗にして繊細な線と空間が織りなす造形の美しさがあります。
また杉岡華邨氏の作品の特徴として、墨の潤渇や墨色の濃淡、文字の大小を生かして水墨画のような遠近感を表現した作品が多くございます。杉岡氏も生前、「絵を眺めるように見てほしい」と常々語っておりました。
現代の日常生活からは遠ざかってしまったかな書の芸術ですが、そこから日本人の精神性や美意識を感じていただければと思います。

▲杉岡華邨氏と中路融人(なかじゆうじん)氏の合作「最上川」。文字の墨の濃淡から奥行きや川の動きを感じることができる
編集部
美術館でこれまでに行われた企画展や今後予定している企画展についてご紹介いただけますか。
松村さん
今年は成田山書道美術館所蔵作品による「松﨑コレクションの古筆と古写経」展を開催しました。
当館では初となる奈良時代の古写経や平安時代の古筆を紹介するもので、今後3年にわたり同コレクションを順次公開していきます。1,000年以上前に書かれた文字のその歴史の重みと、現在でも色あせない美しさを堪能いただければと思います。
また、来年は杉岡華邨氏没後10年となります。そこで、杉岡華邨氏の代表作を一堂に集めその遺徳を偲ぶ展覧会を計画しております。
編集部
季節や時期によって展示内容に違いはあるのでしょうか。
松村さん
展示はおおむね年4期に分け、春と秋には企画展覧会、夏と冬には当館収蔵の杉岡華邨氏の作品による展覧会を開催しております。
※企画展覧会開催時も、杉岡華邨氏の作品による併催優品展は開催しております
企画展覧会では、杉岡華邨氏以外のかな作品や漢字、篆刻(てんこく)作品などもご覧いただけます。かなと漢字それぞれの展示室の全く異なる雰囲気も感じていただければと思います。
「かなの行者」杉岡華邨の生涯と代表作品
編集部
ここまで書道の歴史や楽しみ方をお伺いしてきましたが、松村さんが思う美術館の見どころを教えていただけますか?
松村さん
やはり、美術館の名前の由来にもなっている杉岡華邨氏の作品でしょうか。

▲杉岡華邨氏の作品のひとつ「酒徳」
杉岡華邨氏は書の分野で5人目、かな書の分野では日本初の文化勲章受章者です。その100年近い人生のほぼ全てを書に捧げました。
子ども時代は、奈良県吉野郡下北山村の山々を駆け回って育ち、後に郷里の尋常高等小学校教員として書道の研究授業を担当したことをきっかけに、書の世界にのめり込んでいきました。
その後、辻本史邑、尾上柴舟、日比野五鳳という現代書壇を代表する傑出した書家の教えを受け、作家として頭角を現しました。また、大阪教育大学教授として書道教育の発展や後進の指導に尽力しました。
華やかな活躍の一方で、多くの悩みも抱えていましたが、自らの精神を磨くことでそれらを乗り越え、人間として成長し、「心の書」と呼べるような精神性豊かな作品へと昇華させていきました。
「仮名の行者」と呼ばれるほどの杉岡華邨氏の命そのものと言える「かな作品」の数々をご鑑賞いただければと思います。
編集部
美術館には様々な書道作品があるかと思いますが、松村さんが特に好きな展示やコレクションを教えていただけますでしょうか。
松村さん
特に好きな展示作品は、杉岡華邨作品の「呼子鳥」(よぶこどり、昭和57年制作)です。
呼子鳥は、文字を素材として使いながら景色を作るという、杉岡華邨氏が目指したかな書の代表作です。

▲杉岡華邨氏の作品のひとつ「呼子鳥」。墨の濃淡や太さと細さの違いから奥行きが感じられる。
墨の濃淡やかすれ、文字の大小を生かして左右の集団がそれぞれ近景、遠景となり、真ん中の余白の空間を引き立てながらダイナミックな広がりを感じさせる造形となっています。霧の中にたたずむ山並みなど、見る者の自由な想像力をかき立てる作品だと思います。
編集部
教えていただいたように書道の魅力が詰まった奈良市杉岡華邨書道美術館ですが、自慢できるポイントなどがあれば教えていただけますでしょうか。
松村さん
奈良において、当館は唯一常設の書道専門の美術館です。
多くの社寺仏閣があり歴史を伝える奈良は正倉院文書(しょうそういんもんじょ)をはじめ多くの文字資料が残り、日本の書の発祥の地ともいわれます。
現在も墨や筆が伝統産業として残り、書道文化が盛んなエリアに位置しています。周囲は元興寺の旧境内に広がる「ならまち」と呼ばれる古い町並みが残る最近人気の観光エリアですので、併せて楽しんでいただければと思います。
筆書き体験コーナーで楽しむかな書の世界
編集部
奈良市杉岡華邨書道美術館で体験できることをご紹介ください。
松村さん
美術館内には「筆書き体験コーナー」がございます。
体験コーナーでは墨の代わりに水を使い、専用の半紙に文字を書いていきます。日常生活では毛筆を使う機会が少ないですが、美術館を訪れた際には気軽に筆で書く感触を体験してみてください。水書きなので、失敗を気にせず何度も練習することができます。

▲「筆書き体験コーナー」の様子。テーブルの上に筆や硯、水書き専用の半紙が並んでいる
編集部
イベントやワークショップを実施していれば、ご紹介いただけますでしょうか。
松村さん
企画展覧会に合わせ、様々な講座を開催しております。
例えば、出展作品の解説や作家の制作論についての講演をはじめ、かな書の構成方法である「散らし」に注目し、作品の講評と指導を行う「かなの散らしを楽しむ」を開催しております。「散らし」とは、文字の配置や大きさに変化をつけて美しく紙面を構成する技法です。
また、手書きのオリジナルカレンダーを作る「カレンダーを書こう」などの講座も実施しています。これらの講座は書道の魅力を体験的に学べる良い機会となっています。
編集部
ほかには美術館内で思い出を残せる場所はあるのでしょうか。例えば、写真を撮影できるスポット等があれば教えていただけますか。
松村さん
美術館のポーチには杉岡華邨氏の堂々たる胸像があります。思い出に三人で記念撮影はいかがでしょうか。この胸像は、書道家としての杉岡華邨氏の威厳と芸術性を表現しており、美術館を象徴する存在となっています。
編集部
美術館内に記念のお土産を買うことのできる場所はあるのでしょうか。ある場合はご紹介をお願いします。
松村さん
受付窓口にて展覧会図録、冊子や杉岡華邨氏の作品による絵葉書などを販売しております。ぜひ立ち寄ってみてください。これらのお土産は、美術館での体験を思い出として持ち帰るのに最適です。特に絵葉書は、杉岡華邨氏の作品を身近に感じられる素敵な記念品となるでしょう。
来館者の声に見る杉岡華邨書道美術館の魅力
編集部
美術館を訪れた方からよく聞く感想や声を教えていただけますでしょうか。
松村さん
静かな環境で落ち着いて鑑賞できたとか、かな書の美しさに癒されたとおっしゃる方が多い印象です。特に、書の持つ独特の雰囲気や、作品から感じる作者の思いに共感される方が多いようです。また、書道の奥深さや表現力の豊かさに感銘を受けたという声もよく聞きます。
編集部
美術館はならまち大通りから少し奥に位置していることもあり、閑静な雰囲気が漂っていますね。洗練された環境でゆったりと書道の世界を味わえるのは、来館者の方々にとって魅力的なポイントだと思います。
実際に、Googleの口コミでも以下のような声が寄せられています。

- ならまちに佇んでいる静かな美術館

- 居心地がよかったです

- 絵を見るような感じで楽しめました!

- 公式サイトなどで解説を読んだりしておくとより満喫できると思う
これらのコメントから、奈良市杉岡華邨書道美術館が来館者の皆さんに親しまれ、充実した時間を過ごせる場所として高く評価されていることがわかります。静かな環境や居心地の良さ、作品の魅力、そして事前学習の効果など、多様な観点から美術館の魅力が伝わってきます。
奈良市杉岡華邨書道美術館からカップルへのメッセージ
編集部
デートでの来館を検討しているカップルやご夫婦へのメッセージがあれば教えていただけますか。
松村さん
「かな書は平安時代のラブレターであり、二人の愛をつなぐ大切なものだった」ということを想像しながら、作品をご覧いただければと思います。
かな文字は女手(おんなで)とも呼ばれ、主に女性が用いる文字でした。漢字の草書体を基に、女性の感性で自由に美しく書き崩されて生まれたのです。平安中期には、源氏物語に見られるように、直接対面できない高貴な男女が和歌をやり取りして心を通わせる中で、かな文字の美は芸術として完成されました。
書かれている和歌の素晴らしさだけでなく、かな書はその文字や書きぶり、紙の美しさまで含めて、相手の人柄全てを表現するものだったのです。当時の人々は、文字を通して自分の思いを伝え、相手の心情を想像していました。このような平安時代の恋愛文化を感じながら、二人で作品を鑑賞することで、より深い体験ができるでしょう。
編集部
本日はたくさんのお話をありがとうございました。
杉岡華邨書道美術館の基本情報とアクセス
| 住所 | 〒630-8337 奈良県奈良市脇戸町3番地 |
|---|---|
| アクセス |
【電車】 【車】 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 (最終入館は16:30まで) |
| 休館日 | ・月曜日(祝日の場合は開館) ・祝日の翌日(平日の場合のみ) ・年末年始(12月26日~1月5日) ・展示替えの期間 ※季節や特別展等により臨時開館する場合があります |
| 駐車場 | あり(体の不自由な方用・1台) ※一般の方は近隣の有料駐車場をご利用ください |
| 料金 | 観覧料 一般:300円 ※特別展示の場合は料金が異なる場合があります |
| 電話番号 | 0742-24-4111 |
| 空いている時間帯 | 講演会やイベント開催時を除き、ほぼ常に空いています ※混雑を避けたい場合は平日の午前中がおすすめです |
| 公式サイト | http://www3.kcn.ne.jp/~shodou/ |
※最新の情報は公式ホームページ等でご確認ください。
※記事中の金額はすべて税込表示です。
※展示内容や営業時間等は予告なく変更される場合があります。
杉岡華邨書道美術館周辺のおすすめデートスポット
奈良市杉岡華邨書道美術館は、書道に興味のある人でも約1時間で見学することができる施設です。
ここからは、美術館と合わせて日本文化を体験できるデートスポットを紹介します。紹介するスポットはすべて美術館や近鉄奈良駅から徒歩圏内にありますので、美術館見学後に立ち寄りやすい場所となっています。
おすすめのデートスポット
古民家カフェ「カナカナ」で味わう和のランチタイム
古民家カフェ「カナカナ」は、近鉄奈良駅から徒歩15分、美術館から徒歩6分の場所に位置しています。アクセスが便利で、観光の合間に立ち寄りやすい立地です。
趣のある日本の木造建築を活かした店内には、お座敷席とテーブル席が用意されており、和の雰囲気漂う落ち着いた空間でゆったりとランチを楽しむことができます。伝統的な日本家屋の風情を感じながら、美味しい料理とくつろぎのひとときを過ごせます。カップルでゆっくりと会話を楽しみながら、日本の伝統的な雰囲気を味わえる絶好のデートスポットとしても人気があります。
公式サイト:https://kanakana.info/
鹿とふれあう「奈良公園」散策デート
「奈良公園」は近鉄奈良駅から徒歩10分、奈良市杉岡華邨書道美術館から徒歩12分の場所にあります。美術館で「書道」の世界を堪能したあとは、奈良公園での散策がおすすめです。
奈良公園の魅力は、四季折々の自然美と様々な楽しみ方ができる点です。国の天然記念物に指定されている鹿との触れ合いはもちろん、春には約1,700本の桜、秋には色鮮やかな紅葉を楽しめます。また、1年を通して灯花会や鹿の角きり、東大寺二月堂のお水取りなど、様々な伝統行事やイベントが開催されているのも魅力的です。豊かな自然に囲まれながらの散策は、日頃の疲れを癒し、心身をリフレッシュさせてくれるでしょう。
奈良公園は約660ヘクタールの広大な敷地を持ち、世界遺産である東大寺や興福寺、春日大社などの寺社や奈良国立博物館と隣接しています。園内の売店で鹿せんべいを購入して鹿にエサやり体験をすることもでき、カップルや家族連れにとって思い出に残る体験になるでしょう。
公式サイト:https://www3.pref.nara.jp/park/
地元の雰囲気満点「もちいどのセンター街」でお土産探し
「もちいどのセンター街」は、近鉄奈良駅から徒歩7分の場所にある商店街です。約100軒のお店が軒を連ね、雑貨、服飾、グルメなど多彩な商品を扱っています。
この商店街の魅力は、伝統工芸品を扱う店舗から現代的でおしゃれな雑貨店まで、幅広い種類のお店が集まっていることです。カップルでゆっくりとお店を巡り、思い出に残る記念品や奈良らしいお土産を探すのも楽しい体験になるでしょう。
公式サイト:https://www.mochiidono.com/
奈良の食材を堪能「居酒屋つのふり」で和モダンなディナー

出典:居酒屋つのふり公式サイト
「居酒屋つのふり」は近鉄奈良駅から徒歩1分という便利な場所にあります。
奈良で採れた旬の食材を使った和食や地酒を楽しむことができるため、日本文化を堪能するデートの締めくくりにぴったりのお店です。季節ごとに変わる料理メニューや、奈良の地酒を豊富に取り揃えています。
店内は全て個室となっており、人目を気にせずにゆったりとしたふたりの時間を過ごすことができます。和モダンでおしゃれな内装に加え、小川が流れているなど遊び心のある演出も施されており、落ち着いた雰囲気の中でデートを楽しめます。
公式サイト:https://izakaya-tunohuri-nara.com/
まとめ:かな書と歴史が織りなす奈良の魅力を堪能するカップルデート
この記事では、書道作品を展示する「奈良市杉岡華邨書道美術館」を中心に、歴史ある町並みの「ならまち」エリアを楽しめるデートプランを紹介してきました。
書道の世界、特に「かな書」という優美な書体や作品を鑑賞するだけでなく、歴史あるならまちエリアで見て・食べて日本文化を堪能できるのが、このデートプランの魅力的なポイントです。
普段の生活圏とは異なる、古い町家や寺社が立ち並ぶ「ならまちエリア」を散策することで、ふたりの時間を過ごすことはもちろん、日本の伝統や文化の魅力に改めて気づかされ、お互いに学びのあるデートとなることでしょう。
このデートをきっかけに、カップルやご夫婦で書道教室に通ったり、自宅で書道を楽しんでみたりすると、より書道の世界に親しめるかもしれません。
ぜひふたりの思い出づくりに、奈良市杉岡華邨書道美術館をはじめとする「ならまちエリア」に足を運んでみてください。新たな発見と感動が待っていることでしょう。
結婚したい男性のためのサポートサービスを運営しています

- 理論と実践を徹底マスター!
早稲田大学・森川教授の恋愛学と結婚学 - 恋愛経験ゼロでもOK!
会話からデートまで、すべてをサポート - 90日プログラムで実践力が身につく!
理論と実践の完全マスタープログラム